「白衣、汚しちゃダメじゃない」
「俺、女将さんが頑張ってるの知ってます」
あまりに真剣な小柳君の雰囲気に圧されて、思わず小柳君の目を見つめる。
「女将さんが俺たちのことを、お店のことを考えて、鈴木って人からの申し出断ったのも知ってます」
一言一言を、発する前によく吟味してから伝えてくれていることがわかる。言葉を発する前に目線が下を向き、少し経ってからまっすぐ見つめて伝えてくれる。
「だから・・・。だからこそ、俺たちにもっと背中を預けてください。遠慮なく頼ってください」
「え・・・」
ありがちだ。こういう場面ではありがちな言葉であることはわかっている。しかし、小柳君から出たその言葉は、強い衝撃を私に与えた。
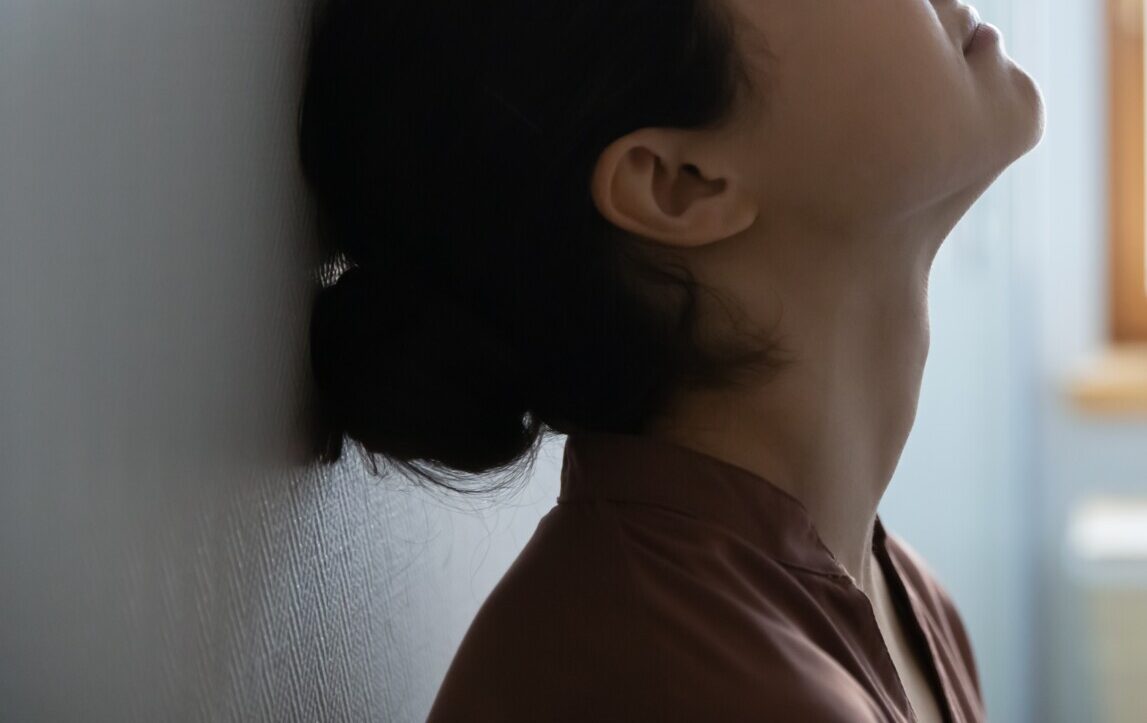
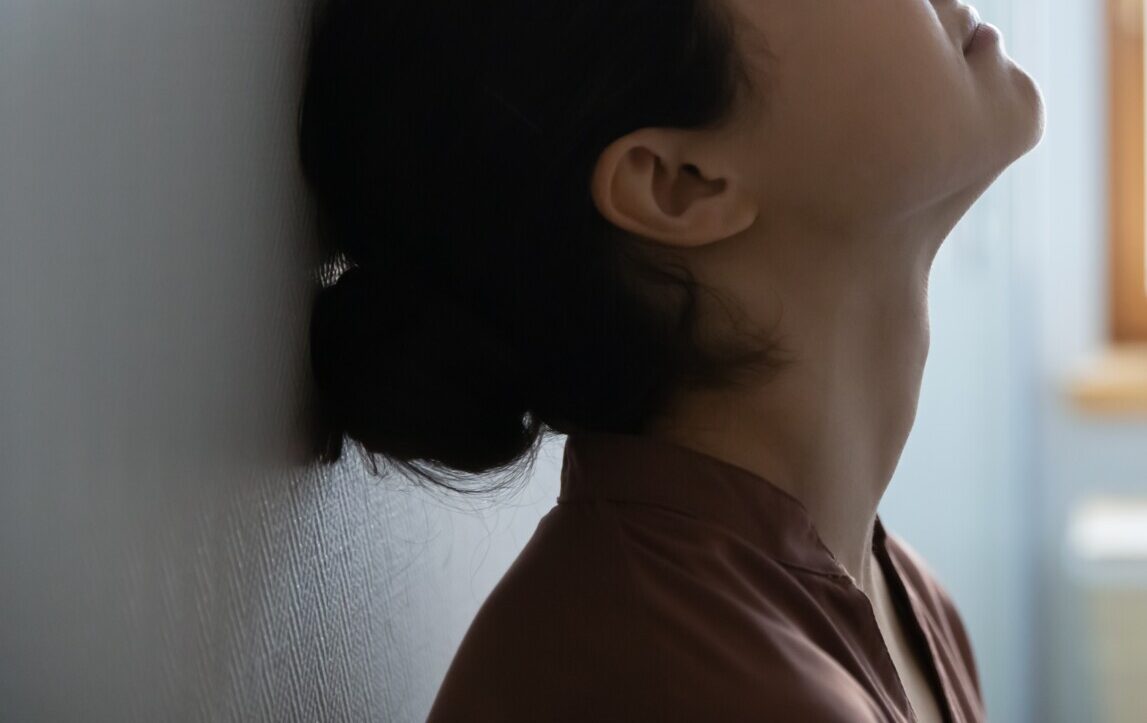
私はいつも彼らを頼っていたつもりだった。お店のためにいろいろな開発や準備をお願いしていたつもりだった。しかし、言われてみると私は、本当の意味で彼らを頼り、一緒に歩もうとできていただろうか。”自分の仕事”を”手伝ってもらう”気になってはいなかっただろうか。
「一緒に、歩かせてください。これだけやってくれてる女将さんと、まだ料理をやっていきたいです」
変わっていないはずの風景が、急に意味を持ち始めた気がした。長良川の堤防を歩く。川の音を聞く。川べりで遊ぶ人を見る。なぜ、これが私を癒してくれるのか。それはたぶん、私と同じ歩幅で時間を流してくれているような気がするからだ。そして、目の前にいる小柳君やお店の美雪さんや久美さんたちも、今の私に歩幅を合わせようとしてくれている。
自然と小柳君に足が向いた。
ありがとう。
言葉は発したつもりだが、ちゃんと声に出せていたかは自信がない。それでも良いと思った。私のダメなところは、きっと彼らが埋めてくれる、足りない言葉は補ってくれる。女将としてのプライドはもちろん大事だ。しかし、それが邪魔をして見えていなかった部分があったような気がする。
「お店に戻りましょう」
夕暮れの空には、白い月が見えていた。
◆